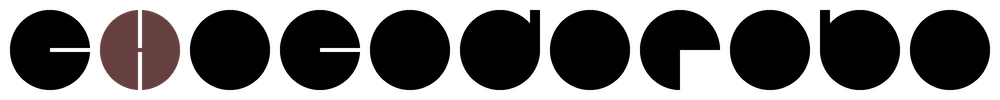今日はお昼から1ヶ月ぶりに岩田さんのラジオに出演する。
(映画『どうすればよかったか?』 についてしゃべりました)
以下は、ラジオで語った内容とは違ってたり重なってたりもしますが、このラジオで喋る前にざっと書いた感想です。
↓↓↓
どうすればよかったか?
カメラという機械が他者になり得る、その可能性が映っていた。映画の中ではしきりに撮影者の存在、そしてカメラという機器の存在について、幾度も言及される。カメラが対象に向けられる時、それは暴力性を孕む。その人間を、その対象が外に向けて必ずしも開示したいと思っていないことすらも、その身体を映し取ることによってこじ開けてしまう。
監督は、姉に向けて、しきりに話しかけていた。思ってることを言って欲しい、聞きたいことを聞いて欲しい。そう投げかけ、姉は時折表情に変化を見せたり、顔を背けたり、あるいはまったく反応をしなかったりする。
父・母・姉・撮影者という4人家族の間に、カメラという機会が挟み込まれる。でもしばらくの間は弟と撮影者はほぼほぼ同化状態にある。つまり弟はカメラのこちら側から両親に語りかけるという構図が続く。それがあるときから、カメラを固定して、弟があちら側に立つことが増える。弟とカメラの分離。この時にカメラのもつ他者性が発揮され始めたような気もする。
姉は、彼女なりの世界、彼女なりの理屈、それを持っている。だがその語りは聞かれることがない。弟が問いかけても、あるいはそれを撮ろうと試みても、両親が先に言葉を発してしまう。あるいは覆い被せてしまう。彼女の世界についての話は聞かれることがなく霧散してしまう。
母の認知症の進行に伴う被害妄想が大きくなり、家族の形態も変化せざるを得ない。皮肉だが、母の妄想(誰かが窓から忍び込んでくる)が、ある意味では他者を招き入れる契機になった。それによって姉は医療につながり、投薬治療によって状況は劇的に変化する。
この家族について、どうすればよかったか?という問い。それにはわかりませんとしか答えようがない。たとえば発症してすぐに医療につながったとしても、映画に映った家の中の状況が、そのまま病棟の中に移されるだけ、あるいはもっとひどい状況になる、という可能性もゼロではないから。いまだに閉じ込めに近いような医療施設はあるし、その劣悪な環境や虐待が問題になったケースもここ数年報道されたりしている。ましてや80〜90年代はさらに状況はひどかったのではないか。だから本当になんとも言えない。
でも言えるのは、ある意味で姉の状態はずっと維持されていた。症状の進行、たとえば「人格の荒廃」のようなことは起きていない。これは投薬や入院治療がなければ取り返しがつかないような状況になる、ということを否定する、あるいは相対化するれっきとしたエビデンスとなるだろう。
もうひとつ、カメラは両親の饒舌さを引き出していたように思う。とくに父の饒舌さ。それは父のサービス精神なのかもしれないし、社会性、外面、そういうものかもしれない。カメラの前で綺麗なこと、都合のいいことだけを語り、不都合なことは隠しているのかもしれないし、言っていないかもしれない。でもそれは嘘ではないし、一面では真実を語っていると捉えるべきだと思う。30年以上の時間をかけて閉ざされた家のなかで築き上げた「真実」は、その父が姉の葬儀の際に発した「姉の人生はある意味では充実していた」という言葉に如実に現れているのだと思う。その時間を、父としてはもはや否定することはできない。肯定はできなくても、間違えているとは、失敗だとは、もはや思えない。だから父の口にした「姉の充実」は、父にとっては本心からのものなのだろう。客観なんてものはそこでは意味をなさない。
カメラが残酷なのは、それらをすべて記録して晒してしまうということである。撮り続けること、記録し続けることは、そしてそれを並びなおして編集して開示することは、その父の「世界」(姉が生きている「世界」とはやはり明確に異なっている)をまざまざと映し出してしまう。この映画に関してはそれが、かなり露悪的なかたちであらわれてしまう。
父はなぜカメラに向かったとてもよく喋ったのだろうか。カメラはそれが向けられた他者の口を開かせてしまうという機能をもつ。その、語りを引き出す装置としてのカメラというものを強烈に意識させるドキュメンタリー作品に、想田和弘の『精神』という映画がある。それは精神クリニックの医師や患者を「観察映画」の手法で記録したものである。そのなかでは、クリニックに通う患者たちがとにかくよく喋る。ひたすらこちら(画面)に向かって話しかけてくる。それだけカメラは誘引力をもつ。
カメラは、その人間を暴露してしまうという暴力性を持つと同時に、語りを引き出す他者性をもつ。統合失調症の有力な治療法として日本でも取り入れられてきているオープンダイアローグは、幻覚妄想も含めた本人の語りをとにかく聞き取る。そして家族や関係者の語りも聞き取る。複数の他者がいる場で、自らの言葉を発する。その継続が、その継続だけを目的とすることが治療的効果をもつ。『どうすればよかったか?』の監督は、カメラが他者になりうる、少なくとも他者性への入口となる可能性を試行錯誤のなかで見つけ出したとも言えるのではないか。そこに、この映画の達成があるような気がする。
このような体験をした当事者の語り(記憶)を見事にエンタメとして立ち上げたのがお笑い芸人2700の八十島だと思う。
ただし、八十島本人は正式な診断名はもらっていないと言及しているので、統合失調症者の語りではなく、あくまでも類似症状を持つ(と私から見える)者としての語り、ということを留保しておく。
八十島の語りを聞き、彼が語る世界に驚きながら聞き入っている千原ジュニアの態度もまた、対話的であり、そこもこの動画の面白さをさらに引き上げている。