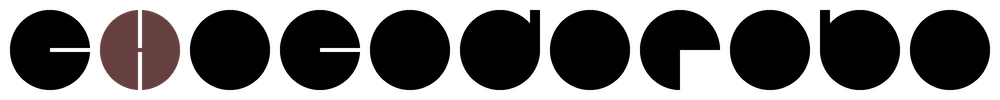新作のリサーチに明け暮れている。ああ、しんど。アルシンド。アルシンドとは鹿島アントラーズにいたナイスヘアのブラジル人FWです。
試しに縦書きでレイアウトしてみました(PC版のみ)。パソコンで見てください。と思ったけど、やっぱりやめました。横書きになおしました。今回まじめなのが多い。

7月20日
もう20日になってしまった。どうしよう、早すぎる。
昨日は、ストレスから過食に走った。それに伴う自己嫌悪があるけど、でも仕方がない。ストレスに晒されたまんまじゃ死んでしまうから、そうなるくらいなら暴飲暴食したっていいのである。太ることは死ぬことの防衛である。人生ミスったと感じた時にはすぐに食に走ること。それも、よりジャンキーなもののほうが望ましい。昨日はよく耐えた、偉いぞ俺。
鬱のときこそ、自分のやりたいことをやろう。それを、事務的にやろう。計画を立て、実行し、記録する。大嫌いなPDCAサイクルをくるくる回す。それがセルフケアとして適している。嫌いな概念や方法もしたたかに取り入れてメンタルをガードするというのが、このクソみたいな世界や時代を生きていく武器になるわけである。忸怩たる思いだが、背に腹は変えられない。命には変えられない。さあこい、PDCA!くるくる回してやるぞ!
てなわけで、今日は何よりも自分を優先する。その時間を大事にする。ごめんよ、仕事。ごめんよ、家庭。ここで踏ん張ることで、その実績をつくることで、明日から義務としての仕事をこなしていけるわけです。
ふと、PDCAの効能について昔考えたことがあったな、と思い出す。PDCAは基本的にシングルタスクに適している。というか、マルチタスクは扱えないものだ。シングルタスクでもいろいろ漏れがあるし目に見えないことや数値化できないものを排除したり軽視したりする傾向が生まれやすい、というのがわたしがPDCAが嫌いな大きな理由の一つだけど、まあなんだかんだ言って計画を策定するのは大事だし、それの進捗をチェックするのも大事だ。わざわざPDCAなんて言っちゃうカブれた感じが癪に触るのである。ともあれ、シングルタスクであれば効果は得られやすい、ということ。あと、PDCAサイクルのワーク(なんか書き込んだり)をすることで、なんか、やった感が生まれる。これが便利なのは、やった感が生まれるので、別にヤンなくてもいいのである。というか忘れてしまう。忘却の装置としてとても有用なのだと思うのです。計画策定と実行については、こんなワークなんかよりそれを相互に管理するチームの方が100倍有用なので、今は傷舐会をやっている。だからやりたくないけどやらなきゃいけないような気がするものをそういったワークに落とし込んでしまえば、逆説的にそれはやらなくてよくなるのである。画期的だぜ、PDCA!
原点に来たら、両隣ともおばちゃんのお客様で、どちらも声量がなかなかのなかです。資料に目を通そうと思ったのだけど、全く入ってこない。仕方がないから日記を書く。声量が大きいというのは結構な手強さですな。イヤホンを忘れてしまったのは悔しい。それはそうと、ノイズキャンセリングってどうなんですか? あれ、ほんとに外の音聞こえないんですか? 気になるんだが。ここで問いかけたところで誰かが答えてくれるなんてことはないし、そうなるとわたしはなんのためにここに質問を投げているのでしょう。
7月22日
昨日からの台風がまだ続いていて、雨風もまだまだぜんぜん強い。昨日も合わせると5連休てなことになる。最近は休みの日の方があまり動けない状況だったのだが、今日は久しぶりに長めの時間が自由になった。本屋さんとか行きたかったけど、雨も強いし断念。今日はアトリエに行こう。その前に原点でゆったり。本を読もうかと思っていたのだけど、なんかやる気が出ない。鬱のせいにしていいのかっていう問題は以前あるが、鬱のせいである。なんでもかんでも鬱が悪いのである。そのせいでわたしは死にたくなっている。わたしを死にたくさせるやつは悪に決まっているわけで、こいつをやっつけないといけないわけだけど、実体を持たないやろうなので、乗りこなすしかないのです。めんどくさい。めんどくさい生き物とはわたしではなくて鬱の方だ。クソ鬱め。
この劇でなにを描けばいいのか。芸術監督が見た、沖縄に住んでいる若者の「熱気」あるいは「肉体の躍動」。それはいったいなんなのか。原作の『逆転』だけではなく、岸政彦の『はじめての沖縄』『同化と他者化』、七尾和晃『琉球検事』などを読みながら探っていたのだが、なんとなく見えてきた道筋がある。それは、「俺たちはここで生きているんだ」ということだ。それは主に『琉球検事』の後半に出てくる部分にインスパイアされたものではある。この本では「コザ暴動」を琉球検察の視点から探っていったものだが、そこで言及されているのは、コザ暴動は単に「反米・反基地」の運動ではなく、日本政府に向けた意思表示なのではないか、ということだった。つまり、これまで自分たちを差別し、冷遇してきた日本という「祖国」に対し、そこに復帰する前に、「俺たちだって日本人だ。日本という国の、ここ沖縄という隅の方で、でもたしかに生きているんだ」、そういうことを叫んでいるのではないか、それがこの本から読み取れることだ。岸政彦も『はじめての沖縄』で、「沖縄とは沖縄に住む人びとのことである」と書いた。そういうことだ。シンプルで当たり前のことだが、ここに私たちは住んでいるのだ、ここに私たちの生活があるのだ、という宣言。その想いを意識的にか無意識にか、身に纏って暮らす沖縄の人々。その発露が、芸術監督の目に「熱気」や「肉体の躍動」として飛び込んだのではないか。
沖縄は「琉球」という独自の歴史を持っている。それをすべて捨てて「日本人」になれ、というのが国がずっとやってきたことじゃないか。自らのアイデンティティを抹消し、日本人に同化せよ、さもなくば日本人にあらず。そういうふうな思想が見え隠れする。そうしていながら沖縄県という地は「日本のもの」だからと、政府の都合で基地を辺野古に移そうとし、県民の意思表示も一切無視して工事を継続している。いつまでこんな思いをしなきゃいけないんだ。いつになったら我々は日本人として認められるのか? 認めないくせに、この土地だけ奪っていくのか? まだ奪うのか? また奪うのか? いつまでも沖縄は、ときに「日本人らしく」、ときに「沖縄人らしく(やさしく柔軟)」という都合の良い存在であり続けなければならないのか。ずっと日本(東京)と対比された「沖縄」という存在でしかいることが許されないことのへ「寂しさ」を、なんだか感じてしまう。
岸政彦『はじめての沖縄』120頁に、沖縄の人々の特徴には「お上に頼らない生き方」というのがあるのではないか、と書いてあった。それは「したたかさ」や「つよさ」のあらわれでもあると同時に「頼”れ”ない」ということでもあるのではないか。最近になってわたしと同年代の人たちの「保守化」がすすんできたように感じるのだけど、それは「お上に頼らない(頼れない)」という特徴と「自己責任論」とが結びついてしまったということではないか。
7月24日
上間陽子さんの、『海をあげる』を上梓した際のインタビュー記事を読む。そのなかで印象的だったのは、「女の子」というキーワード。つまり声を黙殺される存在。どんなに声を上げてもその声は無視され、状況を受け入れていくしかなった「女の子」たち。それに対比されるのは暴力行為をはたらく「男の子」。この構図って、まさに沖縄/本土のそれと同じだ。結局、沖縄の声は無視される。『琉球検事』では「われわれを見ろ!」が最終的なテーゼだったが、この本では「われわれの声を聴け!」ということなのかもしれない。といってもまだこの本を読んではいないので、はやいとこ読まなきゃいけない。これが一番先だ。
今日はこれからジュンク堂に行く。せっかく北谷まで来たけど仕方がない。はやく本を読まなきゃ。『海をあげる』と『日本哲学の最前線』。これを買って家に帰って読むか、アトリエに行くか。距離的には宜野湾に帰った方が近いけど、高速に乗るんだったらどちらでもいいな。それならアトリエまで行こうかな。原点に行ってもいいし。いまコメダだからとりあえずお店を出よう。
ジュンク堂に行き本を買って、原点に戻り(戻り?)本を読んでいる。『海をあげる』はエッセイなので、するすると読めてしまう。だけど、そこに滲んでいる想いはとても複雑で、読む側を圧してくる。
わたしがいま住んでいる宜野湾市真栄原は、「新町」と呼ばれていた場所で、もともと社交場(風俗街)として女性が米兵に身体を売っていた(次第に日本人向けに変わっていく)。ここに引っ越す前に住んでいた場所は宜野湾市喜友名。家から10メートル歩けば、普天間基地のフェンスがあった。その前は浦添市前田、ハクソーリッジという映画にもなった、沖縄戦における激戦地。中部の北側に位置するうるま市石川は、初めに収容所がつくられた場所で、住んでいたアパートの近くにある宮森小学校には1959年に米軍のジェット機が墜落し17名の犠牲者が出た。それから、生まれ育ったのは沖縄市。コザと呼ばれる基地の街で、自宅の下の階には米兵の家族が暮らし、歩いて行ける距離に広大な嘉手納基地の端っこがある。沖縄とは、そういう場所だ。沖縄で暮らすということは、戦争や基地と、その歴史や痕跡と生きていくということだ。それらが生活の中にあらかじめ侵入しているということだ。そこから考えをはじめたい。
演出家からのメモをもらう。そのなかに「人間の怒り、哀しみ、祈りのようなものを実感として受け止められるように」とある。その「怒り」「哀しみ」「祈り」は、きっと沖縄の人にとっては不可視化されたもの、あるいは沈黙させられたものとしてある。つまり、「ないもの」とされている。だからそれが噴き出てきたとき、噴き出した側が非難される。その「ないもの」をどうやって描くか。それがひとつキーになると思う。
また「タクシーというのが何か面白いキーになりそうな気がしています」と演出家。岸政彦『はじめての沖縄』にタクシーの話が出てくる。本土の「常識」から見れば逸脱を行う沖縄のタクシーの運転手たちの自由気ままさから「自治の感覚」を読み取る岸。それは「自分たちのことは自分で決める」というしたたかさであり、「お上に頼らない」ことである。でも反面それは「頼”れ”ない」ことでもある。その視点から『逆転』の4人を見たとき、彼らには「祖国」がなく、自分たちの力で生き、そして助け合うしかなかった。仕事も安次富の兄のところだったり、島から出てきて助け合ったり、そういう自助・共助でしか生きてこられなかった。そうやって助け合って支え合って紡いできた人生を、あっさりと奪って壊してしまう「権力の都合」。その構図を浮かび上がらせるには、どのような方法が可能だろうか。
彼ら4人が奪われたものはなんだろう。戦争を生き延び、戦後を生き抜いて、自ら作ってきた仕事、家族、友人関係、かれらのいられる場所、彼らがそれまでつくってきた生活すべてが奪われてしまった。そしてそのことに異議を申し立てる声も、奪われてしまった。
7月25日
三上智恵監督のインタビューを読む。ものすごくラディカルだ。自身にも社会にもこんなにも鋭く問いかける姿勢に圧倒されてしまった。
・私が伝えたいのは、「沖縄が困っている」ということじゃなくて、日本の民主主義はもう崩壊していて、国民主権は有名無実になっているということ。沖縄の姿を通してそれがわかるんです。
・基地問題は賛成/反対などという単純な問題ではないし、賛成側とは誰のことを指しているのかという疑問はあります。……表面だけを見ているとそれがわからないので、安易な二項対立論を打ち破るためにも、いろんな立場の人にそれぞれの正義があることを個のレベルで、かつ群像で描くことを心がけています。
・つまり、生活のなかに危険があるから、上の人同士が話し合うという問題じゃなくて、一般市民の問題にしなくちゃいけないんです。
・中立とは、言ってしまえば当事者感覚が欠落していることだと思います。沖縄の人たちはみんな、オスプレイが飛んでいる空の下で生活をして、子どもを育てている当事者なんです。つまり、問題との距離がない。中立の立場で俯瞰するなどという発想は、それ自体が沖縄のおかれた状況も、そこを主戦場として生きる記者の存在も理解していないことの証なんです。
・被害者だからといって加害者であることをまぬがれるなんて理屈は通らないと思っています。
・「軍隊は民衆を守らない」という教訓は、沖縄戦を通してもっとも明快に学ぶことができるんです。
・ヘリパッドをめぐる対立がいつしか「県民同士」の対立になってしまう構造
ミーティング前に岡田利規『未練の幽霊と怪物』を読む。〈敦賀〉に出てくる後シテ「核燃料サイクル政策の亡霊」で思ったのは、沖縄の基地問題というのは、日本の軍事政策の夢の亡霊、あるいは民主主義の亡霊、なのではないか、ということだ。